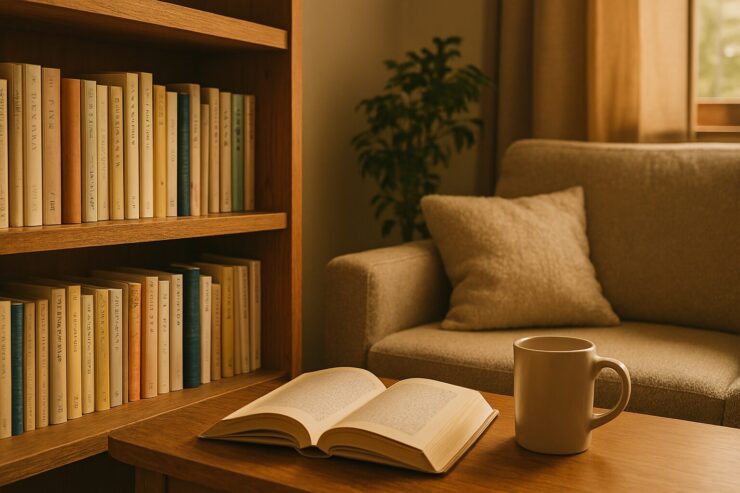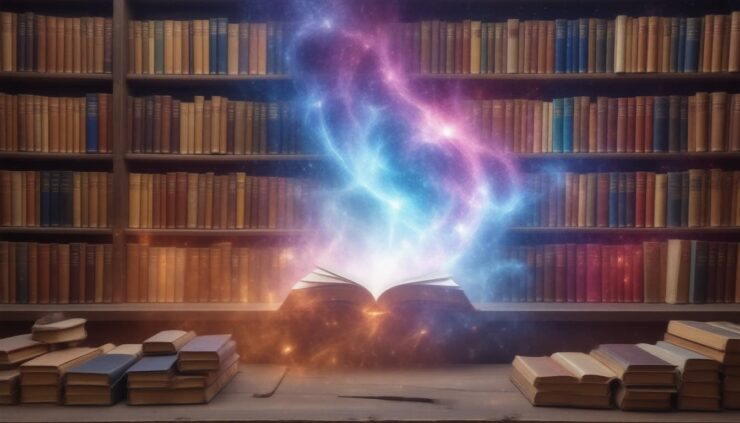「最近、本を読む時間がない」
そんな声をよく耳にするようになりました。
けれど、感性や言葉に触れることを、まるごと諦める必要はありません。
今の時代に合った「読書のかたち」があるとしたら――それは、3分で心を震わせる読書かもしれません。
TikTokやReelのようなショート動画文化の中で、私たちは短くても強い表現に敏感になっています。
その流れに対応しながら、読書の魅力を再構築するヒントをお届けします。
短く読む。でも、深く残る。
今回は、「3分で出会える読書」をテーマに、選書術のアイデアをご紹介します。
目次
なぜ「3分読書」が注目されているのか?
可処分時間――つまり、「自分で自由に使える時間」は、
ここ数年で一気に細分化されました。
スマホの通知、SNSの更新、ショート動画の波。
その一つ一つが、小さな“気の散り”をつくります。
結果として、本を開くこと自体にハードルを感じる人が増えているのです。
けれど、だからといって「読むこと」が不要になったわけではありません。
むしろ、短時間でも感性が刺激される体験への需要は高まっています。
3分で気づきが生まれる。3分で心が動く。そんな本が、確かに存在しています。
短くて深い本の選び方と感じ方
では、どんな本が「3分読書」に向いているのでしょうか?
答えのひとつは、詩集・短編・エッセイのような「断章型」の構成を持つ作品です。
1ページ単位で読んでも、世界観が完結し、
なおかつ余白を残すもの――それが「短くても深い」本です。
たとえば、谷川俊太郎や最果タヒの詩集には、
わずか十数行で世界を変える言葉がいます。
また、吉本ばななのエッセイやヨシタケシンスケの哲学系絵本も、
ページごとに感性を刺激してくれる構成が魅力です。
悪いのは、短さではなく、まったく残らないこと。
「悪くない短さ」は、「余白を手紙にした表現」なのです。
REI式・3分読書のすすめ(ジャンル別ミニ選書も提案)
読書は「まとまった時間がないとできない」ものではありません。
たとえば、朝のコーヒーを飲む3分、移動のまとまめ時間、夜寝る前の静かなひととき。
その短さこそが、感性を研ぎ澄ませる“ちいさな儀式”になるのです。
以下に、ジャンル別でおすすめの「3分読書向けの本」を簡単にご紹介します。
📩【詩】『生きる』谷川俊太郎(読売新聞社):言葉の透明さが、心をそっと撫でる詩集。
🌸【エッセイ】『サラダ記念日』俵万智(沿出文庫):短歌と散文が交差する、日常の小さな光。
🔍【思考系】『りんごかもしれない』ヨシタケシンスケ(ブロンズ新社):遊び心と哲学が同居した絵本。
🌙【感情系】『夜は短し歩けよ乙女』森見登美彦(角川文庫):断片的な読書でも酔える幻想世界。
読むのは、ほんの数ページでいいのです。
「言葉に触れる」ことそのものを、感性のストレッチとして捉えてみてください。
まとめ:3分の余白から、感性の火が燃える
読書は、長く読むもの。
――そんな思い込みを、少し手放してみてください。
短くても、本は私たちの感性に火を灯します。
3分の言葉が、3時間の余韻を残すこともある。
大切なのは、時間の長さではなく、言葉に出会う姿勢です。
忙しない毎日の中で、“余白をつくる習慣”としての読書は、きっとあなたの味方になります。
「忙しいから読めない」ではなく、「短いからこそ読める」読書を。
その小さな一冊が、あなたの明日を静かに変えてくれるかもしれません。